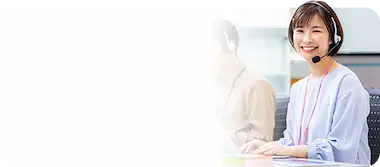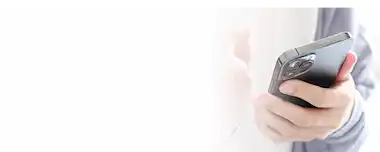家庭用蓄電池の種類と特徴の選ぶポイント
■現在主流の蓄電池の種類
蓄電池は自動車のバッテリーだけではなく、様々なところで利用されています。
携帯電話やノートパソコンモバイル機器の電源などたくさんの用途・分野において利用されており、今や生活に無くてはならないものとなっています。
そんな中、蓄電池と言っても、電池の正極・負極に用いる素材によって4種類に分類されます。
素材によって、安全性の問題や電圧、エネルギー密度、環境への影響といったリスクの大小も異なってくるため、設備の環境や用途に合わせて適切な製品を選ぶことが重要です。
4つの蓄電池の特徴を紹介します。
①鉛蓄電池
鉛蓄電池は、二次電池の中で最も古い歴史を持ち、今でも様々な用途で利用されています。
正極にニ酸化鉛(PbO2)、負極に鉛(Pb)、電解溶液に希硫酸(H2SO2)を用いた二次電池になります。
利用されているのは、自動車のバッテリーを始め、非常用電源やバッテリー駆動のフォークリフト等といった、電動車用電源としても利用され、安価で使用実績が多いため、信頼性が優れているといった特徴があります。
その一方で、繰り返し充電することによって負極の金属に硫酸鉛の硬い結晶が発生しやすく、耐用年数(サイクル数)の増加に伴い性能が低下してしまうという欠点があります。
鉛電池は、極板の種類や構造によって細かく分類することができます。
【極板の種類による区分】
| クラッド式 |
ガラス繊維をチューブ状に編み上げて焼き固めたものの中に極板活物質を充填したもので構成され、長期の使用中でも有害な不純物を溶出する恐れがなく、長寿命が期待できます。 衝撃や振動にかなり強いため、バッテリーフォークリフトの他、通信用・機器操作用・バックアップ電源として利用されます。 |
| ペースト式 |
各子体と呼ばれる極板の骨組みにペースト状にした活物質を塗り込んで極板にしたもので、クラッド式ほどの寿命は期待できませんが、効率放電用途に適しています。 自動車用バッテリーとして有名ですが、無停電電源装置や非常用電源としても利用されています。 |
【構造上の区分】
| ベント形鉛蓄電池 | 液式電池とも呼ばれ、鉛蓄電池発明当時から存在していた構造のもの。
充電中に起こる水の電気分解反応や自然蒸発によって電解液中の水分が失われるため、適宜精製水を補給する必要があります。 |
| 制御弁式蓄電池 |
1980年代半ばより登場したもので、セパレータ(隔離版)に微細ガラスマットを用い、電解液をそのガラスマットに保持する方式をとった構造のもの。ベント形鉛蓄電池の横倒しに出来ないという欠点をクリアし、横置きしても電解液がこぼれない仕組みとなっています。 充電中に発生する水素ガスや酸素ガスを化学反応によって元の水に還元して電解液中に戻しており精製水の補充が不要となっているため、維持運用が容易となっています。 |
②ニッケル水素電池
ニッケル電池とは、正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金、電解液に水酸化カリウムのアルカリ水溶液を用いた二次電池になります。
ニッケル水素電池は高出力・高容量・長寿命の人工衛星用バッテリーとして開発が進められていましたが、当時主流であったニカド電池が及ぼす環境への影響が問題視されるようになり、ニカド電池に変わる乾電池型二次電池として普及してきました。
エネルギー密度が高く、過充電・過放電に強いという特徴から、主にエネループをはじめとする乾電池二次電池やハイブリッドカーの動力源として用いられています。
③リチウムイオン電池
リチウムイオン電池とは、正極にリチウム含有金属酸化物、負極にグラファイトなどの炭素材、電解液に有機電解液を用いた二次電池になります。
例えばニッケル電池と比較しますと、エネルギー密度と充放電エネルギー効率が非常に高く、また残存容量や充電状態が監視し易いといった特長があり、現在の蓄電池の中でも最も普及が進んでおり、技術開発の取り組みも推進されております。
身近なもので言いますと、携帯電話やノートパソコンを始め幅広い電子や電気機器に搭載されております。
④NAS電池
NAS電池とは、正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質にβ-アルミナを用いた二次電池になります。
リチウムイオン電池とも遜色ないエネルギー密度を保ちつつ、鉛電池よりも低価格・長寿命を誇るNAS電池。特長としては、大規模電力貯蔵施設や負荷平準化、工場といった施設のバックアップ用電源として用いられています。
非常に効率よく充放電を行えるNAS電池ですが、ナトリウムと硫黄を使用するために危険物として取り扱われるため、日々の動作確認や保守作業などは必要不可欠でしょう。
4つの種類のまとめ
| 種類 | 特長 | 用途 |
| 鉛電池 | 正極に二酸化鉛、負極に鉛、電解液に希硫酸を用いた電池。低コストで安全性・信頼性に優れている。 | ・自動車のバッテリー
・フォークリフト等電動車の主電源 ・バックアップ電源 |
| ニッケル水素電池 | 正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金、電解液にアルカリ水溶液を用いた電池。常温で作動し、急速充放電が可能。 | ・充電式電池
・ハイブリッドカー ・鉄道システム用の地上蓄電設備 |
| リチウムイオン電池 | 正極にリチウム含有金属酸化物、負極にグラファイトなどの炭素材、電解液に有機電解液を用いた電池。充放電ロスがなく、高出力。 | ・モバイル機器等のバッテリー
・電気自動車への搭載 ・電力貯蔵などの用途 |
| NAS電池 | 正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質にβ-アルミナを用いた二次電池。運転温度が約300度必要だが、長寿命・高密度・低価格。 | ・大規模電力貯蔵
・負荷平準化・系統安定化 ・バックアップ電源 |
■その他の蓄電池システム
【燃料電池】
環境に対して影響のない水素と酸素を利用している「燃料電池」は、次世代の発電システムとして注目されております。
燃料電池は、使い切りの一時電池、充電し繰り返し使用可能な二次電池とは違い、燃料となる水素と酸素を供給し続けることで、電力を作ることができる理想的な発電システムです。
水の電気分解を利用して発電する仕組み、排熱を利用することで既存の発電システムとはくらべものにならない電力を生み出すことができます。しかも、騒音や振動を抑えられ、環境を汚染する物質も生み出しません。
未だ研究段階ですが、今後は水素ガスを使って空気中の酸素と化学反応させることで、燃料電池自動車を家庭用にも適用することが考えられています。
【太陽光蓄電池システム】
ここ数年で、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたものが、一般家庭に浸透し普及しております。
仕組みは、屋根などに取り付けた太陽光発電で電力を創り、それを蓄電池に貯蔵するといったものです。使用される電池には、リチウムイオン電池がほとんど使われており、管理設備などと併せれば、充電状況、電力の使用状況などを数値や図表で管理できます。
太陽光発電システムで貯めた電気は電力会社に売ることができ、日々の生活コストを下げることもできます。
【レドックスフロー電池】
太陽光や風力など、再生可能エネルギーの利用拡大のために必要な系統の安定化技術として期待されている新技術として、レドックスフロー電池があります。イオンの酸化還元反応を用いて充放電を行う電池です。
電極や電解液がほとんど劣化せず長寿命、また材料に発火性のものがないので常温運転ができ、安全性が高いことが特長です。しかも20年のシステム耐久性を持っており、サイクル数は無限で、今後は電力会社や風力・太陽光発電事業者、電力小売事業者や電力需要家など、多くの人々から需要が出てくるでしょう。
■家庭用蓄電池の種類
これまでは蓄電池に使われている電池の種類の解説でしたが。ここからは家庭用蓄電池についてご説明いたします。
まずは、家庭用蓄電池システムに多くみられるのはリチウムイオン電池になります。
リチウムイオン電池を用いた家庭用蓄電池には、コンセントに繋いで使用するタイプ(工事不要)、太陽光発電と連携できるタイプ(配線工事必要)に分けられます。
コンセントに繋いで使用するタイプは、コンセントから充電し、蓄電システム本体についているコンセントに家電製品や照明等を繋いで停電時に活用できます。
太陽光発電と連携できるタイプは、特定の機器(冷蔵庫、照明など)と蓄電システムを接続することで、停電時のバックアップが可能です。
■メリット 停電時に活用でき、電気料金の節約対策
蓄電システムのメリットは、各電力会社によっても異なりますが、深夜の割安な電力を蓄え、電力需要のピーク時に使用することで、電力会社から購入する電力量を抑えることができます。また蓄えた電力を、電気料金の割高な時間に使用することで、電気代の節約にもなります。
太陽光発電システムと連携している場合であれば、昼間に発電した電気を使用しながら余剰分を蓄え、夜に使用することもできますので、いわゆる自給自足することも可能です。
また停電時には、太陽光発電システムの自立運転によって蓄電池システムに充電し、昼夜問わずに電気を使う事もできます。
■デメリット 蓄電容量に限りがあり、置くスペースが必要なこと
蓄電池は製品によって蓄電容量が異なり、家庭用であれば1kWh~12kWhまで様々です。
緊急時に必要な機器が使用できる容量のタイプを選ばないと意味がありません。
リチウムイオン電池は、充放電回数(サイクル数)の寿命を超えると、蓄電容量が減少し、交換が必要になってきたりします。製品によって充放電回数が違いますので、確認が必要です。
また蓄電池は設置スペースの確保が必要になってきます。製品によって、屋外用と屋内用があったり、寒冷地、重塩害地域などには条件があったりします。大きさも違ったりしますので、サイズの確認も必要でしょう。
■低価格化も進み、場所によっては補助金制度あり
従来に比べ、家庭用蓄電池の価格は低下傾向にありますが、蓄電池の容量によって価格が変わってきます。1kWhタイプであれば50万前後で、3~4kWhであれば100万前後で、容量が増えれば金額も増えていきます。また本体価格の他に配線工事や基礎工事など必要な工事もあったりしますので、見積もり内容は確認するようにしましょう。
地方自治体によって補助金が出ている地域もあります。補助金金額や条件、募集期間など異なっておりますので、設置を検討する際は、早めに確認すると良いでしょう。
■プランニングは慎重に 太陽光発電と同時導入のおすすめ
家庭用蓄電池を選ぶ際のポイントは、まず蓄電容量。他には保証内容や停電時の使い方。
容量によって使うことが電気量や時間がことなるので、設置する目的やライフスタイルに適したものを選ぶことが重要です。
これからは、太陽光発電システムと同時に導入することをお勧めいたします。今までは売電単価が高い値段でしたが、今は使う方がお得になってきたりしています。また固定価格買取制度は10年なので、11年以降は蓄電池の需要がきますので、蓄電池をのちのち導入するよりは、初めから導入した方が価格面や配線などの見た目もすっきりしてきます。
■蓄電池+α情報!
太陽光発電の電気が売れなくなる?
2009年に開始されました固定価格買取制度(太陽光発電の制度)の余剰買取が、2019年以降順次10年間の買取期間終了を迎えます。
買取期間終了後、余った電気の買取り先が見つからなかった場合、無償で送電する案が政府から示されております。
詳しくはこちら!