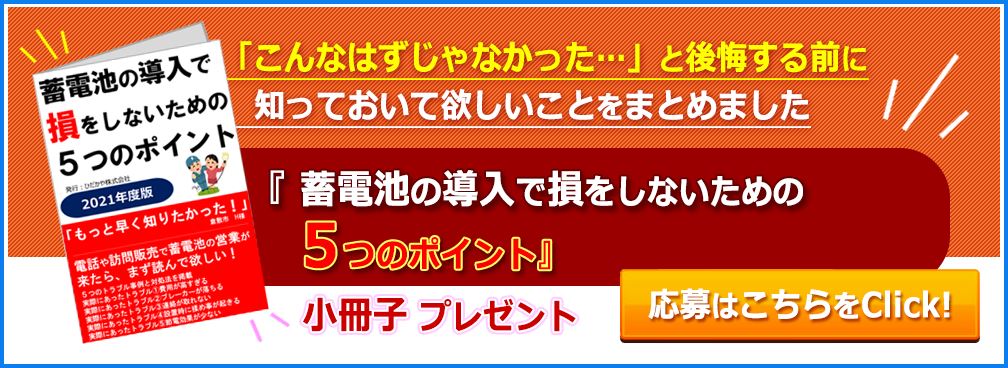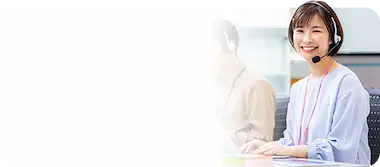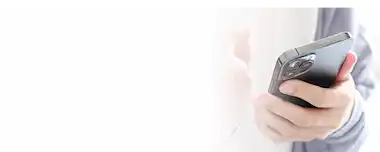家庭用蓄電池の寿命や選ぶうえでのポイント
■家庭用蓄電池システムの寿命
蓄電池システムを検討するうえで、気になるポイントの一つとして「耐用年数(寿命)は?」という質問を頂くケースが多々あります。
蓄電池システムは、導入すればずっと使用したいと思う商品です。ですから何年使えるのか、どう使ったら長く使えるのか気になると思いますので、解説していきましょう。
■蓄電池の種類
エネルギー分野で利用可能な蓄電池は4種類になります。
各蓄電池によって自動車用や出力安定化用として、様々な特色を活かし開発・利用されています。
①鉛電池
特徴
・比較的安価で、使用実績が多く、比較的広い温度範囲で動作。過充電に強く、高電流密度による放電が可能。リサイクル体制も確立。
②ニッケル水素電池
特徴
・溶解析出反応を伴わないので、長寿命が期待でき、過充電、過放電に強い。SOC範囲も極めて広く、急速充放電が可能である。また使用温度範囲も広い。理論エネルギー密度も高く、エネルギー効率も比較的高い。
③リチウムイオン電池
特徴
・エネルギー密度が高く、充放電エネルギー効率が極めて高い。しかも自己放電が小さい。溶解析出反応を伴わないので、長寿命が期待できます。また急速充放電が可能で充電状態が監視しやすい。低いSOCで劣化が起こりにくい。
④NAS電池
特徴
・構成材料が原始的に豊富で、量産によるコストダウンが可能で理論エネルギー密度も高い。また充放電時の副反応がなく(自己放電もない)、充放電のエネルギー効率も高く長寿命。SOC(※1)の利用可能範囲も広い。
※1:SOCとは、State of Charge の略で充電レベルを意味します。
■各種蓄電池の寿命
【各種電池の比較】
| 電池の種類 | 鉛 | ニッケル水素 | リチウムイオン | NAS |
| コンパクト化 | × | △ | ◎ | ○ |
| コスト(円/kWh) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 4万円 |
| 容量化 | ○(~Mw級) | ○(~Mw級) | ○(通常1Mwまで) | ◎(~Mw級) |
| 安全性 | △ | △ | △ | △ |
| 資源 | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 加温の必要性(運転時) | なし | なし | なし | ≧300℃ |
| 寿命(サイクル数) | 17年(3,150回) | 5~7年(2,000回) | 6~10年(3,500回) | 15年(制限なし) |
【鉛電池の寿命】
鉛電池は歴史を持つ古い蓄電池で、安くて安全性を備えています。主に自動車のバッテリーや非常時のバックアップ用電源などを始め、様々なところで使用されています。
サイクル数は3,150回、年数にしておよそ17年となっており、蓄電池の中では長寿命の部類に入ります。他の蓄電池と比較すると充放電サイクルの増加による影響はあまり大きくありませんが、正極に二酸化鉛、負極に鉛、電解液に硫酸を用いているという構造上、過放電した際には負極の金属に硫酸鉛の硬い結晶が発生し、劣化が起きるという特徴があります。
【ニッケル水素電池の寿命】
リチウムイオン電池が登場するまでは、モバイル機器のバッテリーとして用いられていました。今では、主にエネループなどを始めとする二次電池型乾電池として用いられている他、ハイブリッドカーや鉄道用の地上蓄電設備にも採用されております。
サイクル回数は2,000回、およそ5~7年となっており、電池の中でも短い部類です。鉛電池と比べて寿命への影響因子が多く、周囲温度や充放電状況によって寿命が大幅に短くなることは避けられません。
【リチウムイオン電池の寿命】
現代の生活には欠かせないパソコンや携帯電話に使用されています。家庭やオフィスに設置する蓄電池としても普及が進んでいます。
サイクル数は3,500回、およそ6~10年となっておりますが、保存状態や充電方法によって著しく寿命が低下する恐れがあるため、適切に充放電を行わなければなりません。
【NAS電池の寿命】
エネルギー密度が非常に高く、鉛電池よりもコスト面で優れた特性を有していることから、負荷平準化や再生可能エネルギー設備の系統安定化対策や工場を始めとする大規模施設のバックアップ電源として使用されています。
サイクル数は4,500回、およそ15年となっております。
■蓄電池を示すサイクルとはどのような単位?
蓄電池の寿命は年数ではなくサイクル数で表されます。
サイクル数とは、充電と放電をワンセットにした場合どのくらい充放電を繰り返しできるかという回数です。
そのため、充放電の回数が少なくすむ大容量の蓄電池ほど、サイクル数という観点から見ても寿命が長いということが言えます。
■家庭用蓄電池が使われる理由
家庭用蓄電池は、太陽光発電で発電した電気を溜めておくことが目的であります。太陽光発電を設置しているご家庭はほとんど発電した電気をお家で使い、余った電気を売っていると思うのですが、固定価格買取制度は10年と決まっており、10年以降は売らずに溜めることが賢い選択と言われております。
また、大規模停電が起きた際に、家中の電気製品が使えなく恐れがある為、非常用電源として購入する方も少なくはありません。
東日本大震災以降、防災意識も高まっているため、注目が集まっています。
■蓄電池は使用環境や充電の頻度によって寿命が変わる
メーカーカタログ等に記載されている寿命やサイクル数はあくまで目安であるため、使用環境や使い方によっては劣化が早まる可能性があります。
リチウムイオン電池は、過充電や過放電を繰り返したり、極端に高温での環境で使用すれば劣化が早まるとも言われています。
そのため、蓄電池の寿命について確認する際は、蓄電池のご利用環境や使用頻度も考慮に入れることをお勧めします。
■家庭用蓄電池システムの蓄電池の寿命は10年が一つの目安
蓄電池の寿命は、「サイクル」で表記することがあります。「サイクル」とは、充電と放電を1セットとして、何回繰り返すことが出来るかという回数です。同じリチウムイオン電池でも、メーカーによって、その特性などが異なるので、サイクル数も異なってきます。また、充電・放電やその他の周囲環境によってもサイクル数は異なります。
一般的には、蓄電池容量が大きいほど蓄える電力量が大きいため、1回あたりの充放電のサイクル自体も長くなり、寿命を伸ばすことにも繋がってきます。
家庭用蓄電池に採用されているリチウムイオン電池であれば、設置する環境や使用条件にもよりますが、約4千サイクルで毎日使えば約10年程度と言われています。
■寿命を迎えるとどうなる?
10年使用し、それ以降使えなくなるのかというと、必ずしもそういうわけではありません。リチウムイオン電池自体は、充放電を繰り返すたびに少しずつ充放電容量が減っていくという形なので、使えなくなるわけではありません。リチウムイオン電池は、電気自動車として10年程度は安心して使えるように設計されていて、10年使用すると容量が7割前後になると言われています。家庭用蓄電池の中には、電池だけではなく、電子部品や基盤が入っていて、設計寿命が10年に満たないものも少なくないので、部品交換が必要になるケースがあるでしょう。
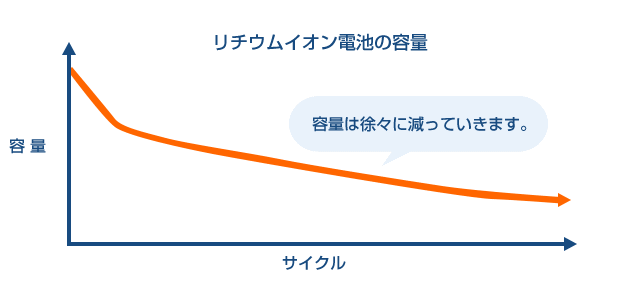
■寿命を迎えたとしてもまだ使える
蓄電池ではなく、購入して使えなくなったら捨てる場合の普通の電池なら、使えなくなった時点で寿命だと判断できると思います。蓄電池の場合は充電をして使えますので、今までの考え方が通用しなくなります。家庭で使われるリチウムイオン電池は充電や放電を繰り返していくたびに、徐々に電池の中の容量が減っていきます。基準と言われている10年ずっと使うと、だいたい7割程度に落ちると言われています。
それよりも、電池の交換が必要になる前に、それらの周辺の電子部品が最初に使えなくなる可能性があります。電子部品の寿命は、一般的に10年物か持たない程度です。長いもので10年以上持つものもありますが、実際はほとんどが10年以下です。
例えばパソコンでいうと、最近のパソコンは充電できる容量が増えてきており1日充電なしで使えたりしますが、3年4年使っていくうちにバッテリーのヘリよりもキーボードやハードディスク等の損傷が気になり始めます。
■蓄電池の保証
このように、蓄電池の寿命が徐々に減ってきます。蓄電池は高い買い物なので、長く使いたいですよね。しかしながら、蓄電池は突然壊れるというわけでもありません。購入してから万が一、数日で壊れたら交換してもらえますが、保証期間が切れて壊れると困りますよね。
そういった事態に備えて、蓄電池の保証期間に注目することも大切です。
蓄電池の保証内容を見る時は、蓄電池本体、出力保証、電力をコントロールする分電盤、リモコンなどの付属部分によって保証内容が異なります。
値段だけにつられず、高い買い物なのでしっかりとした保証が付いている蓄電池を選びましょう。
大手メーカーの保証期間を見てみると、それぞれ違います。
例えば、スマートスターは10年の保証期間がありますが、パナソニックは納品から1年です。またNECは工場出荷から14カ月としています。
このように、各メーカーによって違ったりします。また、お客様は故障が分かればまずは販売店に連絡すると思いますので、しっかりとすぐ動いてくれる販売店を選ぶのも一つのポイントでもあります。
■家庭用蓄電池選びの「比較のポイント」
家庭用蓄電池を選ぶ時のポイントは下記の6つです。
蓄電池を選ぶ際にはどんなことに気を付けて、メーカーを選ぶべきか。
電気代や住環境や生活スタイルに合わせて選んでいきましょう。
①蓄電容量
容量によって使える電力量が異なるので、生活スタイルや太陽光発電の売電量に合わせて選びましょう。
②寿命
充放電の回数には寿命があり、保証されている回数を超えると蓄電容量が減ってきます。蓄電池の寿命はどれくらいなのかということも知っておきたいですね。
③サイズ
メーカーによっても大きさはさまざまですので、設置場所に置けるサイズであるか、事前に現場調査してもらうとよいでしょう
④太陽光発電との併用
太陽光発電を設置している方は、併用した場合にどのような効果があるのか事前に確認しておきましょう。
⑤価格
本体価格の他に、設置工事等の費用も掛かります。また地域によっては、補助金の金額も異なります。見積りを依頼した業者さんに問い合わせてみましょう。
⑥保証
メーカーによっても、保証内容や期間はさまざまです。しっかりとチェックすることをお勧めします。
■家庭用蓄電池各メーカーの特徴と比較
| メーカー | シャープ | パナソニック |
 |
 |
|
| サイクル数 | 12,000回 | 10,000回 |
| 容量 | 4.2kWh | 5.6kWh |
| メーカー保証 | 10年(有償15年) | 10年 |
| メーカー | 京セラ | スマートスター |
 |
 |
|
| サイクル数 | 6,000回 | 6,000回 |
| 容量 | 7.2kWh | 9.8kWh |
| メーカー保証 | 10年 | 10年 |
| メーカー | オムロン | |
 |
||
| サイクル数 | 11,000回 | |
| 容量 | 6.5kWh | |
| メーカー保証 | 15年 |
シャープ
・コンパクト設計で、設置しやすい。例えば4.2kWhであれば高さ605mm、横幅500mm、奥行360mmなのでコンパクトでたっぷり蓄電できます。
・電気使用量や設置場所に合わせて、最適な蓄電池。普段の節約、万が一の停電への備えで4.2kWh。大容量タイプでさらなる安心な8.4kWh。室内設置に適したコンパクトな蓄電池6.5kWh。
・シャープならではの、「見守りサービス」と「長期保証」で、設置後も安心。インターネットを通じてエラーが発生していないかシャープがしっかり見守ります。万日、不具合が発生した場合も、すぐ発見・対応するので安心です。また15年保証(有償)は、保証対象機器(蓄電池本体、ハイブリッドパワーコンディショナー、電力モニター、ケーブル、電力センサー、PRPセンサー)が対象できめ細かな内容です。
パナソニック
・パナソニックは商品ラインアップが豊富で、「創蓄連携システム」が魅力で、パナソニック製のエネファームを連携することで更に効果を生み出す。
・3つのモードがあり「経済優先モード」、「環境優先モード」、「蓄電優先モード」があり、ライフスタイルに合わせた運転が可能。
・創蓄連系システムを利用すればHEMSモニターで電気、ガス、水、太陽光発電、エネファームの状況が閲覧でき節電意識を上げることが可能。
・業界初の「壁掛けタイプ(1kWh)」。住居空間をそこなわない,住宅分電盤のようなデザイン。
京セラ
・ハイスペック蓄電池12kWhを搭載。容量が大きいのが特徴で長時間様々な家電製品を使うことができる。
・ご利用時の出力が大きく、通常の連系時定格出力3.0kW、自立運転時2.0kVAが可能。
・お客様の目的に応じたモード設定が可能で、押し上げ効果ありか、押し上げ効果なしのいずれかが選択可能。
・寒冷地での設置範囲が設置環境の周囲温度下限が-20℃。
スマートスター
・大容量の9.8kWhで200vのエアコンを動かせる高出力3kVA。大容量ならではの「もしもの時」にも備えたい蓄電池。高出力なので200vにも対応していますので、安心です。
・停電時は家中の電気を丸ごとバックアップできる「全負荷型」です。
・太陽光発電と併用で電力会社に頼らない自給自足も目指せます。
・モニターも売電量、買電量、家庭の使用量なども確認ができ、タッチパネル で操作も簡単。
・安心の10年保証が付いており、蓄電池本体およびエネルギーモニターに10年保証がついています。
オムロン
・世界最小・最軽量サイズのコンパクト設計。場所を選ばずわずかなスペースにも設置可能。
・簡単後付けでコストも抑えられる6.5kWhと9.8kWhと16.4kWhタイプがあり、ご家庭のスタイルに合わせ選べます。
・重塩害対応なので海岸線近くでも設置可能です。
・電気を短時間で充電したり、一気に放電もできます。これから本格化する分散電源システムへの対応もできます。
東芝
・ビジネス用途に開発してきた二次電池SCiB™を採用し、長寿命かつ高い安全性を実現。
・安心の10年間保証。蓄電池本体と蓄電システム用分電盤を10年間保証。また、10年間蓄電池容量維持率を60%まで保証。
・エネルギー計測ユニットとの組み合わせで更に便利になり、モニター画面で家庭内の電気使用状況を確認でき、蓄電池モニターで操作画面を表示し操作可能。
■まとめ
今は、家庭用の蓄電池は広く普及しているのがリチウムイオン電池です。これから蓄電池の導入をご検討の方は鉛とかの電池ではなく、リチウムイオン電池にするとよいでしょう。
■蓄電池+α情報!
蓄電池は今後安くなるの?という質問が多々聞かれます。いくらかは安くなると思います。ただ蓄電池にはいろんな材料が含まれていますが、今電池に欠かせないレアメタル(希少金属)やコバルトの国際価格が上昇しています。
コバルトはリチウムイオン電池の正極材に使われています。需要が伸びる一方、銅とニッケルの副産物であるコバルトの供給量はすぐに増やせないとの見通しが強く、品薄状態から17年に高騰しています。現在でも供給がタイトで、価格の上昇が続いています。
ですから今後、住宅用蓄電池が安くなるとは言い切れなく可能性もあり、2019年問題に影響する可能性もあるでしょう。